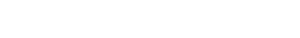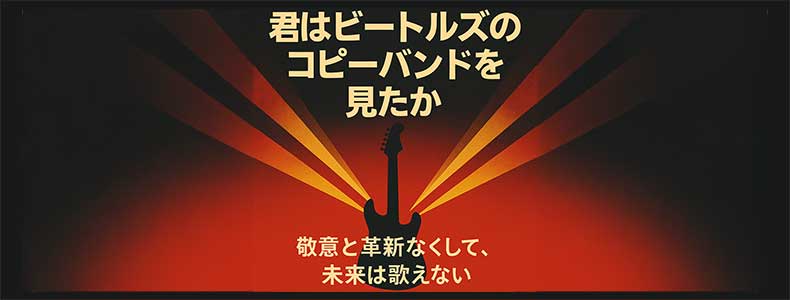古いメモ帳にあったこの問いは、現代の歯科業界のあり方を考える上で、深く示唆に富む視点を与えてくれる。
ビートルズには数えきれないほどのコピーバンドが存在する。彼らはオリジナルへの深い敬意を前提に活動しており、ファンもその姿勢を理解している。演奏技術や解釈は批判されても、存在そのものは肯定され続ける。なぜなら、その活動の根底に「ビートルズを愛している」という揺るぎない前提があるからだ。
では、もしコピーバンドが「曲は悪くないが、ジョンやポールはたいしたことはない」と言い出したらどうだろう。創作の源泉に依存しながら、その源泉を切り捨てるという倒錯が白日の下にさらされた刹那、ファンは幻滅し、静かに去っていくはずだ。
この構図は、現代の歯科業界にも重なる。
特定の臨床モデルを自院で採用し、患者に利益をもたらす限り、それは歓迎されるべきだ。しかし、そのモデルを生んだ哲学を語れぬまま、あたかも自らの教えであるかのようにセミナーで広めるのは、節度を欠いた振る舞いと言わざるを得ない。その核心を生んだ哲学を語れない者に残るのは、空虚な模倣の響きにすぎない。
さらに一線を越えるのは、模倣でありながら「自分こそ元祖だ」と振る舞うことである。それは文化的正当性を巧妙にすり替える、看過できない行為にほかならない。短期的には喝采を集めるかもしれない。しかし、長期的には信用を失い、本質を理解する人々は必ず離れていく。文化的な正当性は模倣や虚飾によって築かれるものではなく、根底にある哲学と、その積み重ねからしか生まれないからだ。
真正の価値は、模倣や小手先の差別化からは決して生まれない。原点を築いた人への敬意と、理不尽なまでの追従、そしてそこから発展させる真の革新によってのみ、長期的な評価は確立される。
メディカルトリートメントモデルの革新性を本当に目指すなら、ビートルズの「Tomorrow Never Knows」がそうであったように、既存の枠を突き破る創造性が必要だ。
予防歯科の歴史的象徴を担うのなら、「A Day in the Life」のように時代を映し出す表現力が求められる。
――それでも君は歌えるのだろうか?