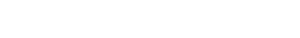高市総理の所信表明演説で掲げられた「健康医療安全保障」と「攻めの予防医療」の徹底は、長らく全身の健康の入り口として重要性が叫ばれてきた歯科医療、特に予防歯科にとって、大きな追い風となる可能性があります。
しかし、この政策を真に国民の健康増進に結びつけるためには、現在の制度が抱える二つの根深い課題、すなわち「財源制度設計の根本的な矛盾」と「医療の質の担保」から目を背けることはできません。
- 疾病保険の限界と「公費インセンティブ」への転換
現在の日本の健康保険制度は、基本的に「疾病保険」、つまり病気になった際のリスクを分散し、治療費を給付する仕組みです。この構造的な限界があるため、「予防」という未病への働きかけに対し保険給付を行うこと自体が、制度の根幹に矛盾を生じさせています。
予防に保険財源を回せば、本来の目的である疾病治療に必要な財源を圧迫し、制度の持続可能性を損ないかねません。私たちはこの矛盾を回避し、国民の主体的な健康行動を促す制度設計が必要です。
そこで注目されるのが、高市総理も言及した「給付付き税額控除」など、公費(税金)を基盤としたインセンティブの活用です。
自ら予防歯科を受診し、健康に投資した国民に対し、その費用の一部を税から還元(控除・給付)することで、「自立した国民」の予防行動を支援します。
たとえば、年2回以上のメンテナンス受診や唾液検査などの科学的リスク評価を実施した者に対して、一定額の控除を設ける、といった制度設計が考えられます。
これは、保険という「治療ありき」の枠組みから脱却し、「健康への主体的な投資」を国が評価し、促すという、より先進的な政策転換を意味します。
予防の財源を保険料から公費へと分離することで、疾病保険の限界を突破しつつ “攻めの予防医療” を現実の仕組みとして実装できるでしょう。
- 質の低い医療への「バラマキ」の停止と専門性の評価
現在、歯周病治療の安定期治療(SPT)に対する保険給付の減額が見込まれるなど、財源の逼迫が顕在化しています。しかし本質的な問題は、医療の「質」が担保されていない治療にまで、一律に給付が行き届いていることにあります。
学会関係者の非公式な見解として、「基本的な歯周病治療ができる歯科医院は全体の20%程度」という指摘もあるように、質の低い医療機関にまでSPTなどの保険点数を“バラまく”ことは、効果のない治療に公的財源を投じることを意味します。
それは、患者の健康を損なうだけでなく、真に知見と技術を持つ医療機関の経営努力を評価しないことにもつながります。「健康医療安全保障」を担保するためには、予防医療の質の平準化が不可欠です。
そのために、以下の2つの改革が求められます。
(1)施設基準の厳格化
SPTなど予防効果の高い保険診療行為については、実施できる歯科医院に専門医・認定医の在籍や研修実績など、より厳格な施設基準を設けるべきです。
単なる届け出制ではなく、研修・実績・データ提出を条件とした「資格制限型基準」として運用すれば、実質的な質保証が可能になります。
(2)データに基づく公的評価と第三者監査の導入
電子カルテやデータヘルスを活用し、実施された予防行為が実際に患者の健康改善に寄与したかを客観的に評価することが必要です。
さらに、学会や公的認証機構による第三者評価を制度化し、診療報酬と連動する形で定期的に監査することで、医療の質を可視化し、国民が信頼できる医療環境を整備できます。
効果の高い医療機関を診療報酬上で優遇する仕組みを導入すれば、
「数」ではなく「質」で報われる健全な競争が生まれ、結果として国民全体の健康増進につながります。
- 新しい「健康医療安全保障」のかたち
保険財源は、「誰に」給付するか、つまり自立した国民に、
そして「どこに」給付するか、つまり質の高い医療機関に、
この2つの軸を明確にすることで、はじめて真に国民の命と健康を守る「安全保障」となり得ます。
予防歯科は、単に病気を防ぐための手段ではありません。
それは、国民一人ひとりが「自分の健康をデザインする力」を取り戻すための社会的仕組みです。
保険から公費への転換、そして質の高い医療への再配分、この制度改革は、
国民の主体的な健康づくりを支え、未来世代の医療費を抑制する“国家戦略としての予防歯科”を築く第一歩となるでしょう。
編集後記的補足
この提言は、「制度改革」と「臨床品質」を両輪として捉えることを目的としています。
予防歯科の真価は、医療費抑制ではなく“人が健康に生きる時間の最大化”にあります。
その価値を支える制度こそが、次代の日本医療の土台になると考えます。
参考:高市総理所信表明:健康医療安全保障
国民の命と健康を守る事は重要な安全保障です。
人口減少・少子高齢化を乗り切るためには、社会保障制度における給付と負担のあり方について、国民的議論が必要です。超党派勝つ有識者も交えた国民会議を設置し、給付付き税額控除の制度設計を含めた税と社会保障の一体改革について議論して参ります。野党の皆様にもご参加いただき、共に議論を進めて参りましょう。
これまでの正当感合意も踏まえ、OTC類似薬を含む薬剤自己負担の見直しや、電子カルテを含む医療機関の電子化、データヘルス等を通じた効率的で質の高い医療の実現等について、迅速に検討を進めます。
高齢化に対応した医療体制の再構築も必要です。入院だけではなく、外来・在宅医療や介護との連携を含む新しい地域医療構想を策定するとともに、地域での競技を促します。加えて、医師の偏在是正に向けた総合的な対策を講じます。合わせて、新たな地域医療構想に向けた病床の適正化を進めます。
こうした社会保障制度改革を進めていく中で、現役世代の保険料負担を抑えます。当面の対応が急がれるテーマについては、早急に議論を進めます。
また、「攻めの予防医療」を徹底し、健康寿命の延伸を図り、皆が元気に活躍し、社会保障の担い手となっていただけるように取り組みます。特に、生差別に由来した健康課題への対応を加速します。私は長年、女性の生涯にわたる健康の課題に取り組んで参りましたが、「女性の健康総合センター」が設立されました。本センターを司令塔に、女性特有の疾患について、診療書店の整備や研究、人材育成等に取り組むなど、その成果を全国に広げて参ります。