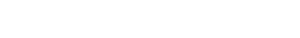日本プロ野球(NPB)の長い歴史の中で、
最もイノベーターであった人物は、間違いなく仰木彬です。
0→1 をつくり、日本人選手の未来を切り開いた「開拓者」——野茂英雄。
その異質さを“才能へと変換する力”を持ち、
イチロー、大谷翔平、山本由伸といった“世界を変える個性”を咲かせた「育てるイノベーター」——仰木彬。
日本人メジャーリーガーの系譜をたどると、
必ずこの二人の哲学の交点に行き着きます。
野茂は「前例を壊した人」
仰木は「異質を活かす仕組みを作った人」
この二つが揃わなければ、
いま私たちが見ている日本野球の黄金期は存在しなかったでしょう。
仰木は「型にはめる」指導を嫌い、
選手のバックグラウンド・性格・価値観のすべてを肯定し、
その人だけが持つ“最高の伸びしろ”に光を当てました。
彼は異質を矯正するのではなく、
“異質のまま強みに転化させる”日本唯一の指揮官でした。
歯科医療は、いまだ“仰木彬的イノベーション”の途上にある
一方、日本の歯科医療はどうでしょうか。
制度、保険点数、旧来の診療フロー——
こうした枠組みが強く働くなかで、
患者一人ひとりの背景や生活ストーリーが
診療に十分反映されないまま進んでいく現場は、いまなお少なくありません。
しかし予防歯科、とくに MTM(メディカルトリートメントモデル)は本来、
“個の違いを読み解き、その人固有のストーリーを治療計画に組み込む診療体系”です。
これは仰木彬が選手に向き合った姿勢と、驚くほど重なります。
仰木彬の“異質を見る眼”は、なぜ歯科に必要なのか
仰木は、他人が欠点と見た部分を、
唯一無二の武器として育てました。
・二軍で凡庸と見られた選手に“別の角度の価値”を見出す
・年齢・経験に縛られず、旬を逃さない起用をする
・前例や常識ではなく「本人らしさ」を尊重する
これはそのまま、
・リスク評価型予防歯科
・個別化したメインテナンス
・ライフステージごとの疾病予防
という現代歯科の核心と一致します。
患者ごとに
生活リズムも、家庭環境も、性格も、口腔内の条件も違う。
その違いを“異質”とみなして切り捨てるのではなく、
“その人の物語”として尊重する姿勢がなければ、予防歯科は根づきません。
米国スポーツの包容力に学ぶ
——ドジャースの強さは「異質の共存」にある
ロサンゼルス・ドジャースのクラブ文化は、
トランプ的排他性とは対照的に、
宗教・肌の色・家族観・価値観の違いを“戦力化”できる大きな器を持っています。
多様な背景を持つ選手が同じロッカーに集い、
互いの違いを尊重しながら競い合う文化。
この包容力こそ、圧倒的な強さを支える要因です。
歯科医療も同じです。
・正社員の衛生士
・子育て中のパート衛生士
・若手のドクター
・ベテランの院長
・時間のないビジネスパーソン
・不安が強い高齢者
・学校や部活で忙しい子ども
こうした背景の違いを尊重し、
一人ひとりに合わせたコミュニケーションと予防プランを設計する。
それができて初めて、予防歯科は文化として根づきます。
仰木彬がいたから、大谷翔平がある
“異質が異質のまま世界で輝く”構造をつくった人。
仰木彬は「異質」を否定しなかった。
むしろそこに未来を見ました。
もし仰木がいなければ、
大谷翔平の二刀流は現実として開花しなかったかもしれません。
イチローの精密な打撃も、山本由伸の世界基準の投球も、
ここまで鮮烈には響かなかったでしょう。
仰木は、
異質を異質のまま認め、
光が当たる位置に配置し、
強みに転換させる環境をつくった人物です。
歯科業界も「仰木彬的アップデート」を
これからの歯科のスタンダードは、
“画一的な治療を正しくこなす医院”ではなく、
“異なる個を理解し、伸ばす医院”です。
患者ごとに違うリスク・違う生活・違う価値観を丁寧に読み込み、
「その人だけの予防計画」を設計できる医院こそ、
予防歯科時代の中心になっていきます。
仰木彬が野球界に残したものは、
スポーツだけの財産ではありません。
医療、人材育成、組織づくり——
あらゆる分野に応用できる普遍的な哲学です。
今、予防歯科にこそ必要なのは、
・野茂英雄が切り開いた 0→1 の精神
・仰木彬が体現した 異質を活かす眼力
この二つがそろったとき、
日本の歯科は静かに、しかし確実に変わり始めると信じています。