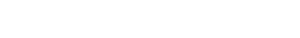歯科医療の流れを振り返ると、1990年代から2020年代へと続く約30年は、
日本の歯科界にとって静かだが大きな価値観の転換が起きた時代だった。
その変化は劇的ではなく、むしろ水面下でゆっくりと、
しかし確実に医療の基盤そのものを書き換えていった。
今回のコラムでは、かつて歯科界を照らした“大御所”たちが
なぜ姿を消していったのか、その背景を歴史的な視点で整理してみたい。
大御所の時代——“語る人”が価値になった頃
1990年代、日本の歯科界には確かに“大御所”と呼ばれる存在がいた。
銀座・赤坂・青山といった場所に診療室を構え、
それぞれが勉強会を主催し、
アクロバティックで華のある症例を披露し、
受講者たちはその技術に魅了された。
当時の価値観は非常にわかりやすかった。
誰が言ったかが医療の価値を決めていた。
- あの先生の言うことなら正しい
- あの勉強会が推奨する手技なら間違いない
- この治療を習得すればキャリアが開ける
治療の中心は歯冠修復と欠損補綴であり、
華やかで劇的な症例こそが“実績”となる時代である。
しかし、この時代の頂点にいた人々の活躍を横目に、
歯科医療の世界は静かに動き始めていた。
予防という新しい視点が日本に根づき始めた
1988年、スウェーデンからアクセルソン博士が来日した。
その講演は、日本の歯科界に初めて体系的な“予防”の概念をもたらした。
当時はまだ、一部の熱心な臨床家が反応しただけだったが、
歯科医療の新しい方向性を示す大きな一歩だった。
続く1990年代、
熊谷崇先生を中心にヘルスケア歯科研究会が誕生し、
予防歯科が臨床の現場に少しずつ浸透していく。
ただしこの時期は、治療中心と予防中心の考え方が混じり合う
汽水域(きすいいき)のような時代だった。
どちらが主流になるのか、歯科医師たちは迷いながら道を探っていた。
エビデンスが「カリスマの言葉」を越えていった瞬間
予防が臨床に根づき始めた頃、
歯科医療の判断基準は大きく変わり始めた。
カリエスやペリオの学びが
“理論”ではなく“臨床で使うもの”となり、治療の方向性を決める際に
もっとも重視されるのは次第にこうなっていった。
“誰が言ったか”ではなく“何が証明されているか”。
つまり、
- カリスマの言葉 → 参考情報
- 科学的根拠 → 判断基準
という構造の逆転が起こったのである。
この価値観の変化こそが、大御所たちが静かに姿を消し始めた最大の要因だ。
彼らが間違っていたのではない。
ただ、医療の評価の軸そのものが変わったのである。
「俺の症例が証拠だ」という時代の終焉
比較検証が難しい時代には、華麗な症例写真や特異なアプローチが
そのまま価値として成立した。
しかしエビデンスベースが広がると、医療の評価軸は完全に変わった。
- 成功率
- 再治療率
- 長期アウトカム
- 患者のQOL
- 残存歯数
これらが数値として可視化されるようになり、
“うまくいっている気がする”という曖昧さは徐々に排除されていった。
そしてこの変化は、大御所の時代が終わったというよりも、
歯科が「歯冠修復・欠損補綴を中心とする技術職の時代」から脱皮し、
科学的根拠と健康維持を軸に据える“医療としての歯科”へ進化したことを
何よりも雄弁に示している。
歯科技工的な職人気質から、医学的な再現性を求める時代へ。
これは歯科の歴史における大きな転換点だった。
ブランド医療から「再現性の医療」へ
大御所の強さは、属人的な技術の高さにあった。
- この先生にしかできない
- この医院だけのノウハウがある
しかし、EBP(Evidence Based Practice)の普及は
価値の中心を大きく変えた。
誰がやっても一定の成果が出る医療。
手品のような技術ではなく、
データとプロセスに裏づけされた医療が求められるようになった。
こうして、
ブランド医療から“再現性を持つ医療”へと価値が移っていったのである。
この変化をどう読み解くか
1990年代から続いた価値観の転換は、
日本の歯科医療にとって大きな意味を持つ変化だった。
かつて大御所が主役だった時代から、
科学と再現性を基盤とする医療へと流れが移り、歯科界は静かだが確かな前進を遂げてきた。
そして今、この転換点をどう読み解くかは、
これからの歯科医療を選び取る一人ひとりに委ねられている。
その背景を整理し、
次の時代へ進むための判断材料として提示することに、今回のコラムの意義がある。